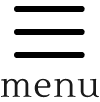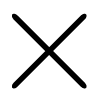たま樹の「 日本舞踊 コラム」
2025/09/07
コラムその7『日本舞踊の起承転結』
今回は日本舞踊の一般的な全体の構成について『君が代松竹梅』の歌詞と共にお話ししようと思います
ポピュラーな現代音楽は
【イントロ→1番Aメロ・Bメロ・サビ
→2番Aメロ・Bメロ・サビ・(Cメロ)→間奏→大サビ→アウトロ】
というイメージがあります
日本舞踊にも基本的な構成があり、起承転結のような展開になっています
【置き→出端→クドキ・語り→踊り地→チラシ】
それぞれに意味があり、大きな流れになっています
・置き
幕開きから人物が登場するまでの演奏、情景が伝わり世界観が見えてきます
置きがないこともあります
・出端
演目の主旨や雰囲気を伝えます
登場人物がはっきりしている演目では職業や特徴を表現します
・クドキ
登場人物の心情を表現したり、経験したことを再現したり
人間味が強く現れる部分です
・踊り地
ここで大きく一転して空気感が変わります
軽快な速いリズムで、文字通り「踊る」部分です
・チラシ
演目の主旨へ戻って、改めて「まとめる」部分です
人物が登場してきた時に手に持っていた物を、再び手にして終わる事が多いです
長唄『君が代松竹梅』
天保十四(1843)年
歌詞を所々に抜粋し、(あくまでも)私の意訳イメージでのご紹介です
置き唄はありませんが、鶯の鳴き声と能管(笛)のヒシギ(音色)から始まります
鶯による「春の訪れ」と能管による「神の使いの訪れ」
出端
御祝儀物という御祝いの世界観です
厳かながら明るい音楽で、松と松から連想される三保松原の羽衣伝説より天女が登場します 
君が代は 恵みかしこき高砂の
松の栄えや限りしられぬ いつまでも
入る日残れる松蔭に 天の羽衣稀にきて
色香ゆかしき 霓裳羽衣の曲をなし
天津御空に乙女子が 鞨鼓を打って舞ふよ
「この世は恵みを頂いて 高砂の松がいつまでも青色をたたえているように栄えています
夕陽の照らす松の木に羽衣をかけた天女が現れて 神の世界の音楽を奏で 鞨鼓を打ち天空を舞う」
クドキ
昔、竹は雪の相方として描かれていた為に雪の風景で竹を表現しています
しっとりとした音楽に、竹のような一筋さの心情です 
降りつむ雪を踏み分けて 夜半にや君が通ひ路も
いつか逢瀬を一筋に 言葉の露の玉章と
くらべこしなる振分髪の長かれと
「降りつむ雪の中でも 夜中になればあなたはここに来てくれるかしら
いつか逢瀬をと一筋な想いが 手紙の言葉に宿る露のよう
まだ幼く分けた短い髪が早く長くなれとばかりに待っています」
踊り地
「梅づくし」で可愛らしい詞と華やかな音楽で恋を踊ります 
誰が袖ふれし匂ひ梅 包むに余る恋風に なびく心のしだれ梅
咲きそめしより鶯の いつか来馴れてほの字とは
はなれぬ中じゃないかいな
「あなたの袖がふれて梅の香りがするのかしら 隠しきれない恋の風 揺れる心は垂れ梅のよう
咲き始めから訪れて来る鶯は ほれた と鳴いているみたいよ
離れられない二人だなんてね」
チラシ
爽やかな疾走感で吉祥と長寿を祝い
穏やかに「めでたいこと」と踊り納めます 
栄えさかふる常盤木は 千歳の松の色かへぬ
げにまた梅は花の兄 南枝はじめて開きそめ薫りは世々に呉竹の いく万歳と限りなく 齢寿く鶴亀の 寿命長久繁昌と 尽きせぬ宿こそめでたけれ
「常に栄えて千年色を変えない松 年の一番始めに咲く梅は世に香り 万年と限りない悠然とした呉竹
鶴亀のごとき齢を寿ぎ 繁栄を祝う
尽きることのない家のめでたいこと」
日本舞踊の基本的な構成が分かると、見ていて理解しやすくなります
お稽古していて「次のクドキはどんなだろう」「踊り地が楽しみだなぁ」と先へ進むことが面白くなります
次回『日本舞踊のレシピ』
これから年内、集中したい事が沢山あるのでいつ書けるのか不明です💦
投稿までお時間頂きます